相続・遺贈・死因贈与により取得した
全ての財産が課税対象となります。
では具体的に課税財産とは
どのようなものなのでしょうか。
預貯金 |
現金・預貯金・定期預金 当座預金・郵便貯金・定期積金 金銭信託など |
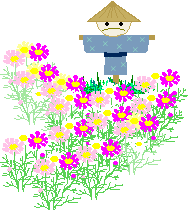 土地 土地 |
田・畑→自作地だけでなく 貸付地も借地も含む。 宅地→居住用宅地、事業用宅地のほか 貸付地、貸家建付地、借地など |
| 家屋→自用家屋、貸家、店舗など 構築物→駐車場など |
|
| 株式→上場株、非上場株 公債、国債、地方債、 社債など |
|
| 商品→商品、製品、原材料等 設備→機械設備、器具、自動車など 売掛金、受取手形、営業上の貸付金など |
|
| 家具、書画 骨董品、貴金属 電話加入権、家庭用パソコンなど |
|
 その他 その他 |
立木、果樹、特許権、 著作権、ゴルフ会員権 事業に関係の無い船舶や自動車 未収の地代、配当金 生命保険契約に関する権利など |
●本来の相続財産
●みなし相続財産
| 死亡保険金 | 被相続人の死亡によって支払われる 生命保険金や共済金で、 被相続人がその保険料を負担していたもの。 |
| 死亡退職金 | 被相続人が受け取るはずだった 退職金や功労金などで、死亡後に 遺族に支払われたもの。 |
| 生命保険契約 に関する権利 |
被相続人が保険料を負担していた 生命保険契約で 相続時に保険事故が発生していないもの |
| 定期金 年金契約 に関する権利 |
被相続人が掛け金を負担していた 年金契約などで 相続時には年金の給付事由が 発生していないもの。 |
| 定期金・年金の 受給権 |
被相続人の死亡後に遺族が受給できる契約に なっている一時金や年金の受給権 |
| 退職年金の 継続受給権 |
被相続人が受給していた退職年金で 被相続人の死亡後は遺族に継続して 支給されるもの。 |
| 信託受益権 | 遺言によって相続人や受遺者に 与えられることになった 信託の受益権 |
| 債務の免除益 | 遺言によって債務が免除される事に なった場合の免除額に相当する分 |
その他
●相続前3年以内の贈与
●相続時清算課税制度
(相続時清算課税制度の適用をうけた
生前贈与がある場合には相続財産となります)
金銭的に価値のあるものについては
原則すべて相続財産とされますが
例外としていくつかのものには様々な理由から
非課税対象のものがあります。
| ▲墓地や仏壇、仏具、神棚、神具、香典など (商品や骨董品として所有しているものは 含まない) |
| ▲相続人が受け取った保険金のうち、一定の額 生命保険は相続税の課税対象となるのが 基本ですが被相続人が残された遺族の生活の ために残した財産ですから相続人が取得した 場合には一定額まで非課税として 認められます。 限度額=500万円×法定相続人の数 例)保険金5000万がおりて 妻一人子二人が相続した場合 500万×3人=1500万 5000万円−1500万円=3500万円は課税対象 |
| ▲相続人が受け取った死亡退職金のうちの 一定の額 |
| ▲相続財産を国や自治体に寄付した場合の 寄付財産 |
| ▲相続財産を特定公益信託に支出したときの額 |
| ▲公益事業を行う人が取得した財産のうち 公共事業に使うもの |
| ▲心身障害者共済制度における給付金の受給権 |
![]() 遺言書
遺言書
○遺言とは・遺言のメリット
○遺言書を書くべき人はこんな人
○遺言の種類
(自筆証書・秘密証書・公正証書)
○遺言の具体的な書き方
○自筆証書遺言書き方サンプル
○遺言でできる事
・身分に関する遺言(認知や成年後見等)
・相続に関する遺言
・遺言執行に関する遺言
○遺言の取り消し
○遺贈とは
・特定遺贈と包括遺贈
・遺贈の放棄
・死因贈与との違い
○遺言執行者とは
![]() 相続
相続
○相続人と法定相続分
○相続の欠格・相続人廃除
○相続人が行方不明の場合
相続人が未成年の場合
相続人が意思表示出来ない場合
○相続の承認
(単独承認・限定承認)
○相続の放棄とは
○遺産分割協議
遺産分割協議書
○特別受益者
寄与分制度
○指定相続分
法定相続分
遺留分減殺請求
![]()
○課税財産・非課税財産
![]() 山崎行政法務事務所
山崎行政法務事務所
取扱業務
![]() 事務所概要
事務所概要
(Iタウンページより)
![]() リンク集
リンク集
![]()
山崎行政法務事務所
営業時間 平日9時〜20時 土日祝日対応可
メールはこちらから
0466-88-7194